
子どもの成長過程で誰もが通る「イヤイヤ期」。
しかし、忙しい日々のなかでついイライラしたり、放置してしまったりする親も少なくありません。
本記事では、イヤイヤ期を放置するとどうなるのか、どんな影響が子どもに現れるのかを詳しく解説します。
さらに、怒鳴らず、放置せず、親子で乗り越えるための具体的な対応策も紹介します。
目次
イヤイヤ期とは?なぜ起こるのか

イヤイヤ期は自我の芽生えのサイン
イヤイヤ期とは、1歳半ごろから始まる「なんでもイヤ!」と主張する時期を指します。
これは子どもにとって重要な発達の一段階。自分という存在に気づき、「自分でやりたい」「思い通りにしたい」という強い欲求が現れます。
イヤイヤ期が始まる時期とピーク
イヤイヤ期の始まりは個人差がありますが、一般的には1歳半〜2歳頃。
そして、2歳〜3歳前半でピークを迎えることが多いとされています。
ピーク時には、何をしても「イヤ!」、「自分でやる!」と主張が激しくなり、親も疲弊しやすくなります。
しかしこの時期を過ぎると、4歳ごろには感情のコントロールができるようになり、イヤイヤは徐々に落ち着いていきます。
イヤイヤ期に見られる主な行動パターン
- やろうとしていることを急に拒否する
- 服を着たがらない、脱ぎたがらない
- 「自分で!」と言い張り、大人の手助けを拒む
- 怒りやすく、泣き叫んで癇癪を起こす
- 欲しいものを手に入れられずに床に寝転がる
イヤイヤ期を放置するとどうなる?

子どもの情緒発達への悪影響
子どものイヤイヤを無視したり、適切に関わらずに放置すると、情緒の発達に悪影響を及ぼす可能性があります。
「どうせわかってもらえない」という学習が進み、感情をうまく表現できない子どもに育ってしまうかもしれません。
自己肯定感の低下につながるリスク
イヤイヤ期に自分の気持ちを受け止めてもらえない経験を重ねると、自己肯定感が低くなるリスクもあります。
自己否定感を持つ子は、挑戦を避けたり、人間関係を築くのが苦手になる場合もあります。
親子関係が悪化する負のスパイラル
イヤイヤを放置されると、子どもはさらに反抗的な態度を強めることがあります。
これに親がさらにイライラし、怒鳴ったり叱ったりすると、親子関係の信頼が崩れやすくなります。
怒鳴るとどうなる?怒りの影響

怒鳴られることによる心理的ダメージ
怒鳴ることで一時的に行動は止まるかもしれませんが、子どもには恐怖心と不信感だけが残ります。
心の安全基地である親を怖がるようになり、感情を抑え込んだり、逆に問題行動をエスカレートさせたりすることも。
怒鳴りたくなったときの対処法
- その場を一度離れて気持ちをリセットする
- 深呼吸を3回繰り返す
- 「今怒るより、どうしたいか」を自分に問いかける
怒りを感じたら、まず自分自身を落ち着かせることが大切です。
イヤイヤ期と癇癪の違いとは?
「イヤイヤ期」と「癇癪(かんしゃく)」は似ていますが、原因も対応方法も異なります。
| 項目 | イヤイヤ期 | 癇癪(かんしゃく) |
|---|---|---|
| 特徴 | 自己主張の表れ | 感情コントロールの未熟さ |
| 原因 | 自分で決めたい、自立心 | 欲求不満、疲労、ストレス |
| 対応 | 選択肢を与え、共感する | 安全確保し、落ち着くまで待つ |
癇癪の場合は無理に止めようとせず、安全を確保した上で見守るのが基本です。
イヤイヤ期への具体的な対応方法

子どもに選択肢を与える
「これにする?それともこっち?」と選択肢を示すことで、子どもの「自分で決めた」という満足感を育てることができます。
子どもの気持ちに共感する
「イヤなんだね」「やりたかったんだね」と感情に寄り添った声かけをすることで、子どもは安心感を得ます。
小さな成功体験を積ませる
自分でできたことに対して「すごいね」「がんばったね」と褒めることで、子どもの自己肯定感が育ちます。
親自身のケアも忘れずに
完璧を目指さず、つらいときは誰かに頼ったり、短時間でもリフレッシュする時間を持ちましょう。
親の心の余裕が、子どもの安定にもつながります。
まとめ|イヤイヤ期は成長の証
イヤイヤ期は、子どもが「自分らしく」育つために必要な試練です。
放置せず、怒鳴らず、子どもの気持ちに共感しながら見守ることで、子どもは安心して自立への一歩を踏み出せます。
親にとっても大変な時期ですが、子どもの成長の大きなチャンスととらえて、無理せず乗り越えていきましょう。
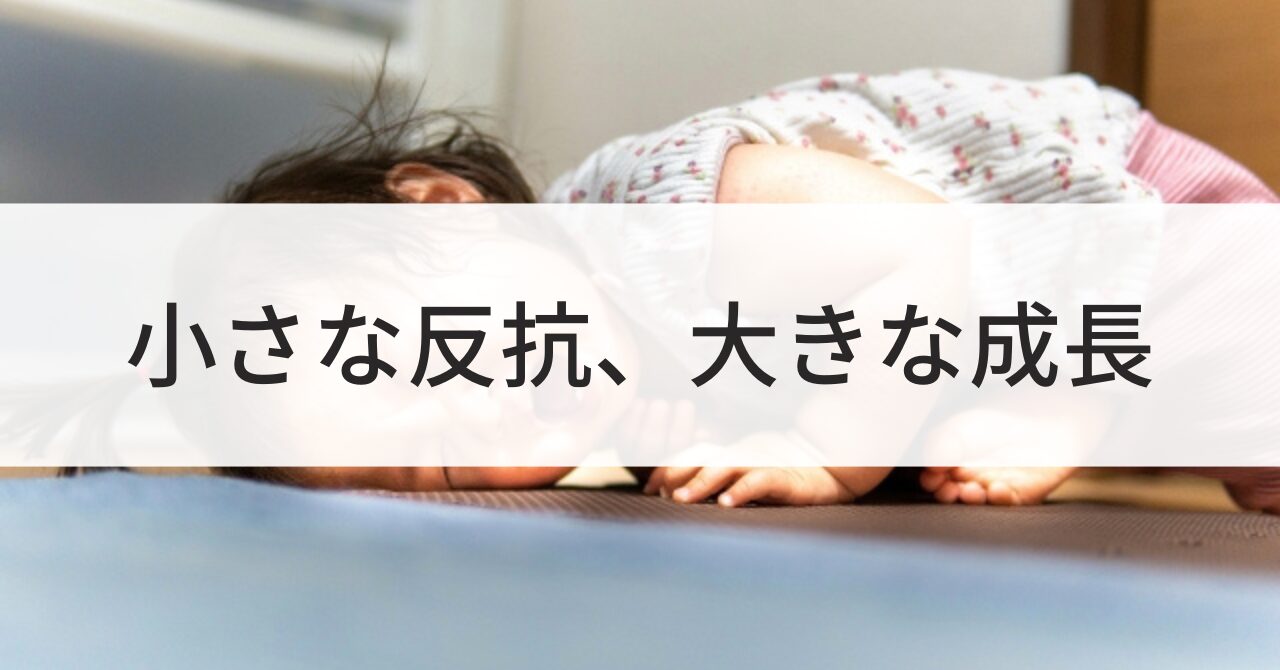

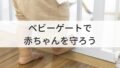
コメント