
積み木は、赤ちゃんから幼児期まで長く楽しめる知育おもちゃです。
ただ、親として気になるのは「いつから積み木を積めるのか?」「どんな遊び方が発達に合っているのか?」という点ではないでしょうか。
本記事では、子どもの月齢に応じた積み木遊びの目安や、成長に合った関わり方をわかりやすく解説します。
さらに、何個積めるのが一般的かという発達の目安や、楽しく学べる遊び方のコツも紹介します。
積み木はいつから使える?月齢ごとの遊び方の目安

初めての積み木は何ヶ月から?
積み木との最初の出会いは、生後6〜8ヶ月頃が目安です。
この時期の赤ちゃんは、「握る・叩く・舐める」などの感覚遊びを通じて、手や口を使って周囲の物を探る段階です。
積み木はまだ“積む”ためのものではなく、素材の感触や音、重さを知るためのツールとして使われます。
この段階では、角が丸くて舐めても安心な木製やシリコン製の積み木がおすすめです。
形や大きさが揃っている必要はなく、むしろ色々な形状に触れさせることで、視覚や触覚の刺激になります。
1歳児が積み木を積む目安は?何個積める?
1歳〜1歳半頃になると、手指の動きが洗練され、縦に積み重ねる動作が少しずつできるようになります。
この時期の子どもは「物を重ねる」「崩す」を繰り返しながら、試行錯誤を楽しむようになります。
発達の目安として、1歳0ヶ月では2個程度、1歳半では3〜4個程度を積める子が多いです。
ただし、個人差が大きいため「積めない=遅れている」と考える必要はありません。
| 月齢 | 遊び方の目安 | 積める積み木の数 |
|---|---|---|
| 6〜8ヶ月 | 握る・舐める・打ちつける | まだ積めない |
| 10〜12ヶ月 | 両手で積み木を打ち合わせる | 1〜2個 |
| 1歳〜1歳半 | 縦に積む遊びに挑戦 | 2〜4個 |
2〜3歳でできる積み木遊びの幅
2歳〜3歳になると、積み木遊びがより複雑で創造的になります。
ただ積むだけでなく、「並べる」「分類する」「何かに見立てる」といった遊びが広がりを見せ始めます。
2歳児の多くは4〜6個の積み木を積むことができ、橋や門、家のような形を意識した構造的な遊びに発展していきます。
この時期には「考える→試す→崩れる→再挑戦」という試行錯誤を通じて、集中力・バランス感覚・空間認知が育ちます。
3歳以降になると、積み木をごっこ遊びに取り入れたり、物語性を持たせたりと、創造力を活かした遊びが自然に始まります。
積み木遊びで育つ子どもの発達|知育の観点から

指先の器用さ・バランス感覚を鍛える
積み木は、単なる遊び道具ではなく、子どもの身体と脳の発達を同時に促す知育アイテムです。
特に積み木を「掴む・持ち上げる・積む」といった動作は、手指の細かい動きをコントロールする力(微細運動)を鍛えます。
また、積み上げる際には「まっすぐ置く」「傾かないように慎重に重ねる」といったバランス調整の力も必要です。
このような経験を繰り返すことで、目と手の協応動作(アイハンドコーディネーション)が育ち、将来的な「書く・食べる・ボタンを留める」などの日常動作にもつながっていきます。
集中力・想像力を引き出す効果
積み木は「遊びながら学ぶ」ことができる代表的な知育おもちゃです。
積み木を積み上げたり、並べて形を作ったりする中で、子どもは集中して考える力を自然と身につけていきます。
例えば「次はどの積み木を置くか?」「崩れないようにどうするか?」を試行錯誤しながら遊ぶことで、課題解決力や論理的思考が鍛えられます。
さらに、動物や家などに見立てて遊ぶようになると、想像力・創造力の発展にもつながります。
「崩れたらまたやり直す」このシンプルな繰り返しも、子どもにとっては失敗を受け入れて再挑戦する力を育てる貴重な学びの場です。
| 育まれる力 | 積み木遊びとの関係 |
|---|---|
| 手先の器用さ | 積む・並べる・崩す動作の繰り返し |
| バランス感覚 | 倒れないように慎重に積む |
| 集中力 | 完成を目指して繰り返し挑戦 |
| 想像力 | 見立て遊びで自由な発想を育む |
積み木はいつまで使える?年齢別の遊び方と工夫

4歳〜6歳でも楽しめる積み木の発展遊び
「積み木=乳児向けのおもちゃ」と思われがちですが、4歳以降も十分に楽しめる知育ツールです。
この年齢では、より複雑な形や高く積むことができるようになり、構造遊びが本格化していきます。
たとえば、橋や塔、建物など対称性やバランス感覚を活かした作品を自分で考えて作るようになります。
積み木を並べて道路に見立てるなど、空間を構成する力やルール性のある遊びにも発展し、想像力・計画性・達成感が育まれます。
また、お友だちと協力して一緒に作品を作ることで、協調性やコミュニケーション能力も育っていきます。
小学生でも使える!?創造力を高める遊び方
小学生になっても、形やサイズが自由な積み木だからこそ生まれるアイデアもたくさんあります。
例えば、「物語に合わせた町を作る」「決められた積み方にチャレンジする」など、遊び方の自由度が高いのが積み木の魅力。
創意工夫を重ねる中で、集中力・発想力・問題解決力などが自然に育っていきます。
また、図形学習や立体の理解にもつながることから、STEAM(科学・技術・工学・芸術・数学)教育の入り口として注目されることもあります。
| 年齢 | 主な遊び方 | 育まれる力 |
|---|---|---|
| 4〜6歳 | 建築・橋・道路などの構造遊び | 創造力・構成力・協調性 |
| 小学生 | 物語性のある作品作り・設計ごっこ | 発想力・集中力・論理的思考 |
モンテッソーリ教育と積み木|自主性を育む使い方

なぜモンテッソーリで積み木が重視されるのか
モンテッソーリ教育は、「子どもは自ら育つ力を持っている」という考えのもと、自発的な活動を大切にする教育法です。
積み木は、そんなモンテッソーリの理念に非常にマッチするおもちゃとして、世界中の園や家庭で取り入れられています。
特徴としては、正解のない遊びであること。
どう積むか、何を作るかはすべて子ども自身が決めます。
その中で、自分の頭で考え、手を動かし、達成感や失敗を味わうことで、自己決定力・問題解決力・集中力などが育ちます。
また、素材や色においてシンプルで本質的なものが多く、派手な音や光を使わないため、子どもが“今ここ”に集中できる環境を作りやすいのもポイントです。
おすすめのモンテッソーリ系積み木とは?
モンテッソーリの考え方を反映した積み木にはいくつかの共通点があります。
無着色または自然素材で、サイズが統一されていたり、数学的概念に基づいた設計がされていたりと、遊びながら数・形・空間を理解できるよう工夫されています。
例えば、以下のような特徴のある積み木は、モンテッソーリ系として評価が高いです。
- 木の質感が感じられる無塗装の積み木
- 同じサイズの立方体で構成されたもの
- 高さや長さが徐々に変化するよう設計された教材型ブロック
こうした積み木は、数の概念・長短・大小の比較といった要素を体感的に学べるため、「遊びながら学ぶ」理想的な教材となります。
積み木選びに迷ったら、「モンテッソーリ監修」や「知育積み木」と明記されているものをチェックするのもおすすめです。
長く使える積み木の選び方とおすすめ商品

年齢・目的別で選ぶポイント
積み木は対象年齢に合ったものを選ぶことで、安全に、そして効果的に遊ばせることができます。
ここでは、子どもの発達段階に合わせた積み木選びのポイントを整理します。
| 年齢 | 選び方のポイント | 素材・特徴 |
|---|---|---|
| 6ヶ月〜1歳 | 口に入れても安心、軽くて大きめ | シリコン製、角が丸い木製 |
| 1〜2歳 | 握りやすく、積みやすい形 | 無垢の木製、正方形・長方形 |
| 3歳〜 | 創造的に遊べるバリエーション | 色つき、曲線、磁石付きなどもOK |
特に形やサイズが揃っている積み木は、積む動作がしやすく、発達段階に合った遊びがしやすくなります。
素材は天然木で塗装に安全性の高い水性塗料を使用したものが安心です。
成長に合わせて長く遊べる積み木3選
ここでは、発達段階に応じて長く使える積み木を厳選して3つご紹介します。
いずれも、安全性・遊びやすさ・知育効果のバランスが良く、親子で楽しめる製品です。
① エデュテ Soundブロックス(LA-008)
音が鳴る積み木やミラー付きパーツなど、五感を刺激する設計が特徴。
カラフルな見た目と楽しい仕掛けで、0歳後半〜3歳以降まで長く使えます。
木製で安心、安全基準にも適合しているので、出産祝いや誕生日プレゼントにもおすすめです。
② ボーネルンド オリジナル積み木
無塗装で舐めても安心。サイズが揃っており、初めての積み木にぴったり。
1歳前後から使えて、形や数に慣れる基礎づくりに最適です。
③ KAPLA(カプラ)ブロック
3歳以上〜小学生でも夢中になれる薄型の木製ブロック。
空間認識や構造理解、創造力を遊びの中で楽しく学べます。
どの積み木も、年齢を超えて遊びの内容が変化していくため、1セットあれば数年にわたって使えるのが魅力です。
兄弟姉妹で共有したり、お下がりとしても使いやすく、コストパフォーマンスにも優れています。
散らかりにくい!積み木の収納アイデア

インテリアになじむ収納グッズ紹介
積み木は細かく数も多いため、床に散らばりがちです。
毎回片付けるのが面倒…と感じている方も多いのではないでしょうか。
ここでは、出し入れしやすく、リビングにもなじむ収納アイテムを紹介します。
- 木製のフタ付きボックス
インテリア性が高く、そのまま置いても生活感が出にくい。重ねて使えるタイプも◎ - キャスター付きの収納ワゴン
子どもでも移動しやすく、遊ぶ→片付ける動作を自然に誘導できる。 - 仕切り付きの収納ケース
積み木の種類ごとに分類でき、遊ぶときも見やすい・探しやすい。
ポイントは、子どもの目線でも積み木が見えるようにすること。
収納が“出すための道具”にもなれば、遊びがよりスムーズになります。
子どもが自分で片付けられる工夫
積み木の収納は「親が片付けるもの」ではなく、子ども自身が楽しんでできるように工夫するのがコツです。
遊び終わったあとに“片付けも遊びの一部”にできれば、習慣化もスムーズです。
以下のような工夫が効果的です:
- 片付け用の目印をつける
積み木の形や色に対応した絵やシールを貼ることで、どこに戻せばよいかが分かりやすくなる。 - タイマーを使って「よーいドン!」
競争形式にすることで楽しみながら取り組める。 - 親子で一緒に片付ける習慣
初めのうちは一緒にやりながら「ありがとう」「きれいになったね」と声をかけることで、達成感を感じやすくなります。
片付けが苦にならない仕組みを作れば、散らかりストレスの軽減だけでなく、子どもの自立心も育ちます。
小さな積み重ねが、将来的な習慣づくりにつながっていきます。
積み木の収納についてはこちらの記事でまとめていますので、ぜひご覧ください。
また、積み木にように創造力を高める遊びについて、こちらの記事でまとめているのでご覧ください。
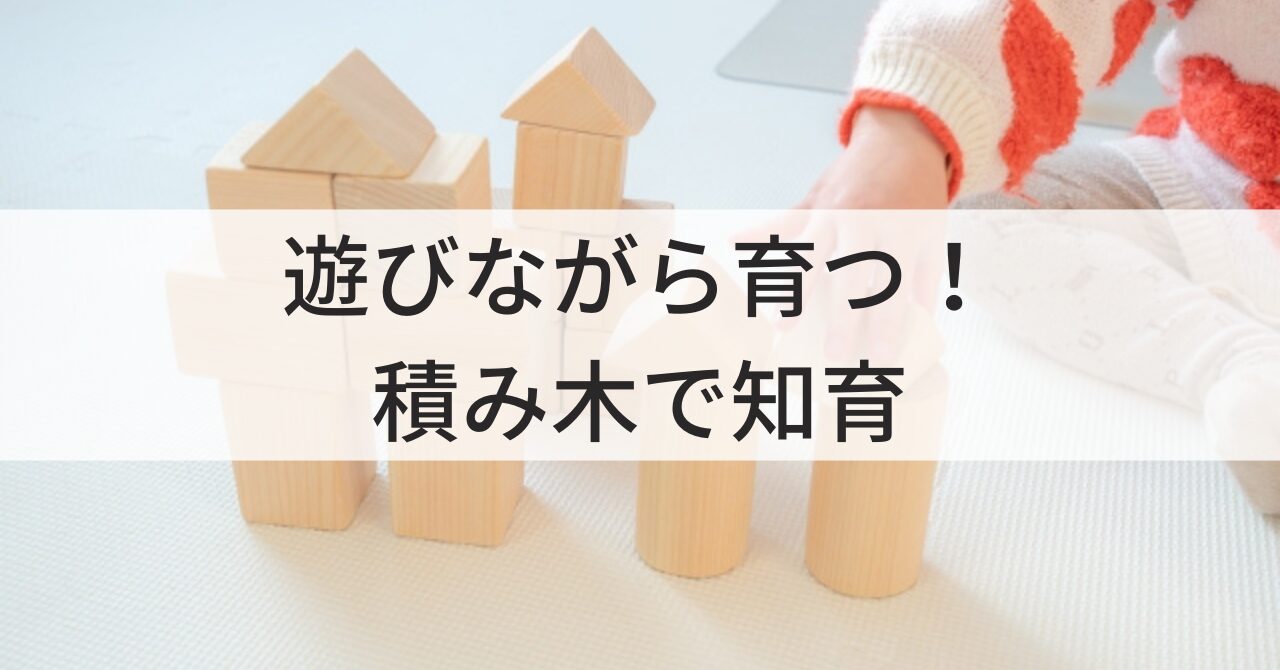



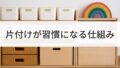
コメント