
子どもがイヤイヤ期になるとこのようなお悩みを抱えてはいませんか?
「何をしても泣いてる子どもにイライラが止まらない」
「ダメだと分っていても怒ってしまう」
「イヤイヤの対応に追われて、家事が全然進まない」

我が家でも子どものイヤイヤ期は頭を悩ませることがいっぱいありました。
ネットで検索すると「子どもの気持ちに寄り添う」なんて書いていますが…、「わかっているいけど、いつもいつもできないよ!」と思ったりしませんか?
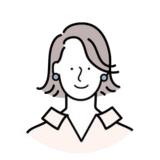
家事も仕事も両立しなきゃいけないのに、そんな余裕はありません…。
親だって1人の人間です。疲れたり、イライラしたりして間違うこともあります。
だからこそ、イヤイヤ対応を乗り切る「仕組みづくり」が大切だと考えています。
そこで記事では、よくあるイヤイヤ期の悩みと、それに対する具体的な対策を3つご紹介します。
少し肩の力を抜いて子どもと向き合えるように、参考にしてみてください。
イヤイヤ期のあるあるな悩み

子どものいいなりみたいでいいの?
「子どもの気持ちに寄り添って」と言われても、なんでも言う通りにしていては甘やかしになるのでは?と不安になりますよね。
でも、実は“受け入れる”ことと“甘やかす”ことはまったく別物。
こちらの記事では、「受け入れること」「甘やかさないこと」をわかりやすく解説してくれます。子どもの甘やかしすぎには注意!自立させる甘えとの違い

記事で紹介されていることを表にまとめてみました。
| 受け入れてOK (甘え) | 甘やかしてはいけない (甘やかし) |
|---|---|
| お母さんの膝に座りたい → スキンシップとして受け止める | 「お菓子ちょうだい」と泣く → 泣けばいつでも買ってもらえると学ぶ |
| 「ボタン留めて〜」とお願いされる → 気持ちに応えて手伝う | 親が「早く!」と急かして子どもの洋服を一方的に着せる |
| 「牛乳入れて〜」と頼まれる → 子どもの不安や寂しさを理解して応じる | 「こぼすから」と親が勝手に代わりに注ぐ |

キーポイントは「自立」につながるかどうかですね。
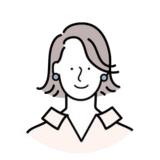
親の愛情を確かめるのも「自立」に重要です。
ずっと泣いていて頭がおかしくなりそう
「何しても泣き止まない」「こっちのほうが泣きたくなる」…そんな日もありますよね。
イヤイヤ期の子どもは感情のコントロールが未熟で、理由なく泣くこともあります。
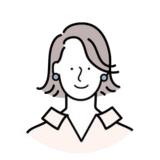
こちらに余裕がなくなってくると、イライラしてしまいませんか?
ご飯を食べないけど大丈夫?
せっかく作ったご飯を「イヤ!」とひとこと。
食べずに遊び出す姿に、心配やイライラが募ります。

健康も心配だし、マナーもこれでいいのか不安になりますよね
でも、イヤイヤ期の食べムラはよくあることで、一時的なものがほとんど。
それはわかっていても、ずっと続くと心配になって当然です。
イヤイヤ期に対応するための対策3選

対策① イヤイヤ期に悩むのは自分だけじゃないことを知っておこう
「こんなにわがままで、うちの子大丈夫?」
頭では“イヤイヤ期”とわかっていても、毎日付き合っているうちに深刻に考えてしまうことってありますよね。
でも安心してください。実は多くの家庭で同じような悩みを抱えているんです。
イヤイヤ期は「1~2歳」がピーク
博報堂の「子育てママ白書2018」によると、1歳(22.9%)と2歳(29.0%)の時期に「子育てで悩んだ」と回答したママが最も多くなっています。
この時期が“イヤイヤ期のピーク”であることが、データからもわかります。
協力者がいないと悩みやすい傾向
また、「パートナーや祖父母の協力が少ない」と感じているママほど、悩みが深刻化する傾向にあることもわかっています。
つまり、「うちの子だけ?」「私の接し方が悪い?」と自分を責める必要はありません。
同じような時期に、同じように悩んでいる親がたくさんいます。
大切なのは「ひとりで抱え込まないこと」。
データを知ることで、「みんな同じなんだ」と安心できるはずです。
対策② かける言葉を決めておこう
「気持ちに寄り添って」「自立を促して」…
頭ではわかっていても、実際にはどう声をかければいいか悩んでしまうこと、ありませんか?
イヤイヤ期は、感情が爆発する場面も多く、こちらも余裕がなくなるもの。
だからこそ“どんな言葉をかけるか、あらかじめ決めておく”ことが、とても助けになります。

実際に我が家で決めている声かけは、次の3つです。
- どうしたの?
- どうしたいの?
- 何をしてほしいの?
この声かけは、ただ気持ちを聞くだけでなく、「イヤ」だけじゃなく「こうしたい」と子どもが気持ちを言葉にするきっかけになります。
実はこの考え方、中学生に対して“自律を育てる声かけ”として使われている方法でもあります。
(出典:リセマム|自律の力を育てる声かけ)
もちろんイヤイヤ期の子どもとは発達段階が違いますが、「指示する」のではなく「引き出す」という姿勢は共通しています。
対策③ 時短サービスを導入することで、親の余裕を増やそう
イヤイヤ期の子どもに向き合うには、何よりも「親の心の余裕」が大切です。
でも実際は、仕事・家事・育児…毎日やることに追われ、気持ちに余裕なんてなかなか持てないのが現実ですよね。
そんな時に頼りになるのが、家事や育児の負担を減らす時短サービスです。
時間を生み出す=心に余白ができる
例えば、「夕食のおかずを作らなくていい」としたら、少し家庭の状況も変わってきませんか?
最近はつくりおきの宅配サービスを利用する方も増え、どんどん家事も外注化が進んでいます。

我が家も実際に導入しました。
おすすめの宅配サービスについてはこちらの記事でまとめています。
また、家事代行サービスで掃除や洗濯の一部を任せるという手もあります。
子どもが小さく、仕事が忙しい時は「時間」が何よりの高級品です。
家族の笑顔を増やすための投資だと思って検討してみてください。
おすすめの家事代行についてはこちらの記事でまとめているので参考にしてみてください。
イヤイヤ期の対応が続かないのは、余裕がないから

「わかっているのに、うまくできない…」
「子どもに寄り添わなきゃ」「ちゃんと向き合いたい」
そう思っているのに、朝の準備や仕事の支度に追われていると、つい余裕をなくしてしまうことってありますよね。

子育てと仕事が重なる時は、本当に自分の時間なんて取れないですからね。
疲れているのに、さらに子どものイヤイヤ
仕事や家事だけでも精一杯なのに、
そのうえで何度も「イヤ!」と泣き叫ぶ子どもに向き合うのは、誰だってしんどいものです。

私のずっと否定されている気持ちになってしんどかったです。
でも自分を責めなくて大丈夫。
笑顔で向き合える自分でいるために、できるところは無理を減らしていきましょう。
イヤイヤ期のNG対応だけは頭に入れておく

理想と現実は別…。
でも、子どものためにやってはいけないNG行動だけは把握しておきましょう。
怒鳴る・無視する・命令する
思わず感情的になって怒鳴ってしまったり、
「もう知らない!」と突き放したり…。
その場では一時的に静かになるかもしれませんが、
怒鳴られたり無視された経験は、子どもの心に不安や不信感を残してしまいます。
また、「早くして!」「ダメって言ったでしょ!」などの強い命令口調は、反発心や自己主張の暴走を引き起こし、かえってイヤイヤを加速させることもあります。
ひとりで抱え込まないで
イヤイヤ期は一人で立ち向かうものではありません。
夫婦で役割を分担したり、家事代行や保育サポートを利用したり、時には友人や地域の子育て支援を頼ってもいいんです。
助けを借りることは、手抜きではなく「家族を守る選択」。
「イヤイヤ期=困った時期」ではなく、「成長を実感できるチャンス」として乗り越えていきましょう。
まとめ
イヤイヤ期は、子どもが「自分」という存在を確立しようとする大切な成長のプロセス。
でも、親にとっては毎日が試練の連続で、心が折れそうになることもありますよね。
そんなときに大切なのは、「理解」「工夫」「余裕」の3つです。
- 子どもの“イヤ”は、自立への一歩だと受け止める
- 伝え方や環境をちょっと工夫する
- 全部を一人で抱え込まず、外の力を上手に借りる
くれぐれも自分1人でどうにかするではなく、「使えるものは全部使う」くらいの気持ちでいてください。
家庭の負担を減らす方法についてはこちらの記事でまとめているので参考にしてみてください。
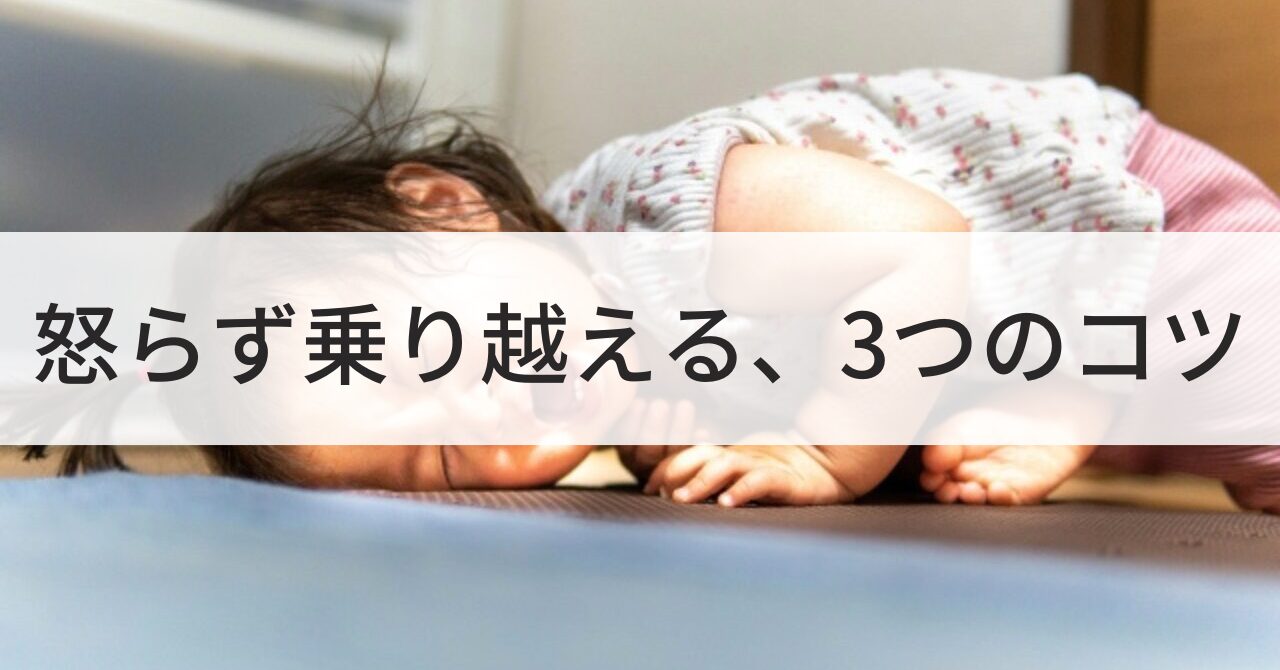

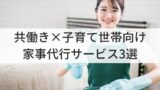




コメント