
「9ヶ月になっても寝返りしない…」
「もしかして発達に問題がある?」
と不安を感じる親御さんは少なくありません。
寝返りには個人差があり、発達の順番もさまざまです。
頭ではわかっていても、実際に寝返りをしない我が子を見ていると、どうしても心配してしまうもの。
そんな方に安心していただくために、本記事では、寝返りしない原因や他の発達との関係、練習方法など解説します。
焦らずに見守りながら、できるサポートをしていきましょう。
9ヶ月で寝返りしないのは普通?

赤ちゃんが寝返りしない原因とは
寝返りをしない赤ちゃんにはいくつかの原因があります。筋肉の発達が未熟な場合や、背中・首・お腹の連携がまだ取れていないケースもあります。
また、体重が重めだったり、おっとりとした性格の子も寝返りが遅くなる傾向があります。
寝返りできるのにしない子の特徴
寝返りが「できるけどしない」子もいます。例えば、周囲に興味がなく動機が生まれにくい場合や、もともと慎重な性格の赤ちゃんです。
また、寝返りよりもお座りやハイハイに興味を示すこともあります。

まだやる気にならないの。
9ヶ月の寝返り平均と比較してどう?
厚生労働省の調査によると、赤ちゃんが寝返りを始める時期は一般的に4〜5ヶ月頃が多く、8〜9ヶ月にはほとんどの赤ちゃんが寝返りできるようになるとされています。
また、母子健康手帳でも「6〜7ヶ月頃に寝返りができるようになる子が多い」と記されており、これは発達の目安のひとつです。
| 月齢 | 寝返りできる子の割合 |
|---|---|
| 4〜5ヶ月 | 約40〜60% |
| 6〜7ヶ月 | 約70〜90% |
| 8〜9ヶ月 | 90%以上 |
9ヶ月時点で寝返りができない赤ちゃんは少数派ではありますが、他の発達(視線・表情・お座りなど)が順調であれば、大きな問題であるとは限りません。
焦らず、全体の成長を見守ることが大切です。
寝返りが遅い・早い子に見られる傾向

寝返りが早い赤ちゃんの特徴
寝返りが早い子にはいくつかの共通点があります。
身体が軽くて動きやすい体格の子や、活発で好奇心旺盛な性格の赤ちゃんに多い傾向があります。
周囲の刺激に敏感で、「動いてみたい」という気持ちが強い子は、比較的早く寝返りを始めます。
寝返りが遅い赤ちゃんは何ヶ月から?
一般的に寝返りは4〜6ヶ月頃に始まりますが、8〜9ヶ月でようやくできる子もいます。
9ヶ月を過ぎても寝返りをしない場合でも、他の発達(お座り・手の動き・表情など)が順調であれば、大きな問題はないことが多いです。
体格や性格が寝返りに与える影響
赤ちゃんの体格や性格も寝返りの時期に影響します。
例えば、体がふっくらしている子は重心移動が難しく、寝返りが遅れがちです。
また、おっとりした性格の子は慎重で、新しい動きにチャレンジするまでに時間がかかる場合もあります。
寝返り以外の成長にも注目

寝返りしないけどお座りはできる?
9ヶ月になっても寝返りをしない一方で、お座りが安定してできる赤ちゃんもいます。
これは、発達の順番が必ずしも「寝返り→お座り」ではないためです。
先に体幹を使う動作が得意な子は、寝返りを飛ばしてお座りに進むこともあります。
寝返り返りができないと心配?
寝返りはできても「寝返り返り(元に戻る動作)」ができないという悩みも多いです。
これは背筋や腹筋、腕のバランスが取れていないためです。
左右どちらかに偏っている場合もあり、発達の途中段階としてよく見られるものです。

うちの子も寝返り返りは、なかなかできなかったです。
発達には個人差があると理解しよう
赤ちゃんの成長スピードは一人ひとり異なります。寝返りが遅くても、その後のハイハイやつかまり立ちで急成長することもあります。
今の時期にできることを見つめ直し、焦らず見守る姿勢が大切です。
うつ伏せが嫌いな子の寝返りサポート
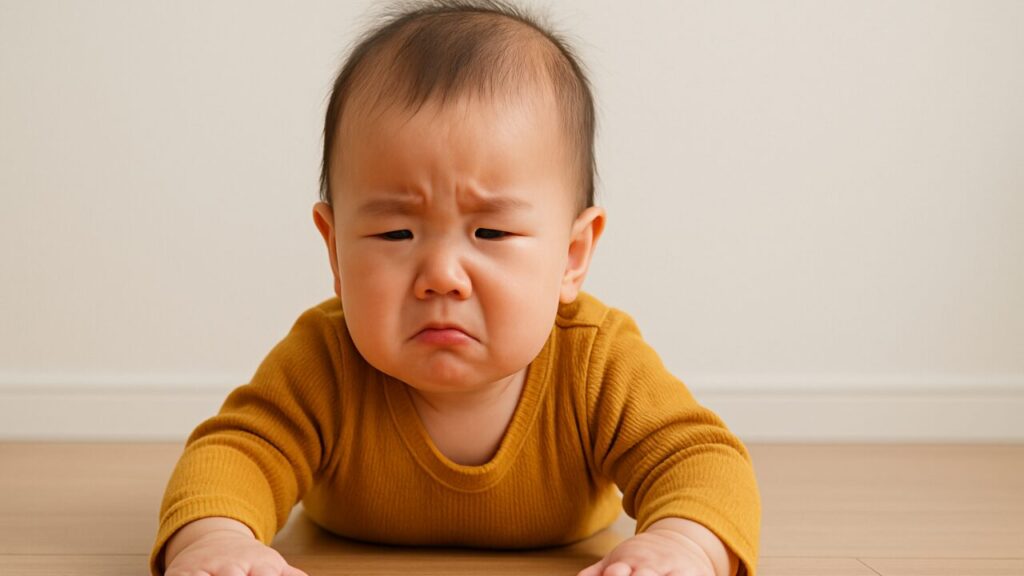
9ヶ月でうつ伏せ嫌いな子の特徴
9ヶ月で寝返りをしない子の中には、うつ伏せそのものが嫌いな赤ちゃんもいます。
顔が床につくのを嫌がったり、うつ伏せ姿勢で動けないことに不快感を感じる場合があります。
泣いてしまうことが多い子も、無理にうつ伏せにさせる必要はありません。
うつ伏せを嫌がる理由と対処法
うつ伏せを嫌がる原因には「首が疲れる」「視界が狭くなる」「不快な体勢になる」などがあります。
対処法としては、ママやパパの顔が見える角度でうつ伏せにしたり、好きなおもちゃを目の前に置くなど、楽しめる環境をつくることが効果的です。

うつ伏せは疲れちゃうの。
寝返り練習のおすすめ方法
うつ伏せが苦手な赤ちゃんには、タオルを背中や脇に入れてサポートしながらの寝返り練習が効果的です。
また、足を少し押して回転を手伝うことで、動きの感覚を覚えることができます。以下は練習方法の例です。
| 方法 | ポイント |
|---|---|
| タオルサポート | 脇にタオルを入れて体を傾けやすくする |
| おもちゃ誘導 | 興味のあるおもちゃを動かして視線を誘導 |
| 脚押しサポート | 片脚をそっと押して転がりの動作を促す |
親ができるサポートと見守りの姿勢

無理に寝返りをさせなくていい理由
寝返りは自然な流れの中で身につく動きです。
無理に練習させたり、できないことを叱ったりすると、赤ちゃんが運動そのものにネガティブな印象を持つ恐れがあります。
本人のタイミングを尊重し、「できたとき」にたくさん褒めることが最も効果的です。
日常でできる体の使い方の促し方
特別なトレーニングをしなくても、日常の中で赤ちゃんの身体を使う機会を増やすことができます。
例えば、床に寝かせる時間を増やし、おもちゃを左右に動かして首を回したり、手を伸ばしたりする環境を意識してつくるだけでも十分な刺激になります。
安心して見守るために知っておきたいこと
発達には幅広い正常範囲があります。
焦る気持ちは自然ですが、他の成長(視線の合い方、笑顔、手の動き)なども見て、総合的に判断しましょう。
自治体の育児相談や健診も活用し、ひとりで抱え込まないことが大切です。
相談すべきサインと対応方法

家庭でチェックしたい発達のポイント
寝返りができないことだけに注目するのではなく、赤ちゃんの全体的な様子を観察しましょう。
例えば、目が合うか、笑顔を見せるか、音に反応するか、手を使って遊ぶかといった点も発達の大切な指標です。
気になる点が複数ある場合は早めの相談を検討しましょう。
いつどこに相談すべきか
心配が続く場合は、自治体の保健センターや、乳幼児健診の機会を活用しましょう。
必要に応じて、小児科医や発達支援の専門機関への相談も有効です。
9〜10ヶ月健診が近い場合は、事前にメモをして質問できるよう準備しておくと安心です。
相談時に準備しておくと良い情報
相談の際には、寝返り以外の成長状況(離乳食・睡眠・視線の動きなど)を伝えられるようにしておくと、より適切なアドバイスがもらえます。
写真や動画をスマホに残しておくのも効果的です。
発達は多面的に評価されるため、「できること」にも注目しておきましょう。
まとめ|焦らず赤ちゃんのペースを見守ろう
- 9ヶ月で寝返りしない赤ちゃんもいますが、発達には大きな個人差があります。
- 筋力や性格、体格などが寝返りの時期に影響します。
- お座りや手の動きなど他の発達が進んでいれば、心配しすぎる必要はありません。
- うつ伏せが苦手な場合は、無理をせず楽しめる練習から始めましょう。
- 不安があるときは、保健センターや小児科で気軽に相談してみてください。
寝返りだけにとらわれず、赤ちゃんの「できていること」に目を向けることが大切です。
「ハイハイ」についてもこちらの記事にまとめてみましたので合わせて読んでみてください。
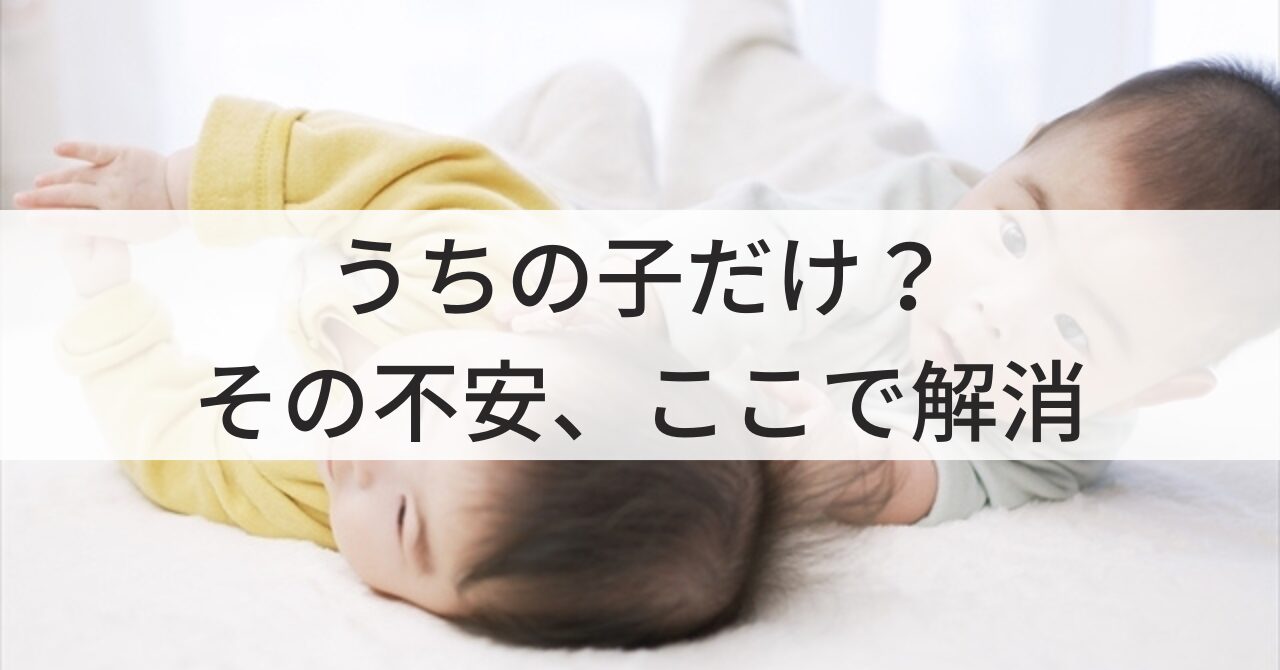


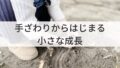

コメント