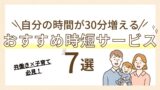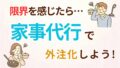※本サイトで紹介している商品・サービス等の外部リンクには、アフィリエイト広告が含まれる場合があります。
「移動で小さい子どもがいるけど遠方に通勤しないといけない…。」
「単身赴任は嫌だけど、あまりに時間を無駄にしている気がする…。」
このようなお悩みを抱えたことはありませんか?

私も高速で片道1時間半の通勤を2年したことがあるよ。
片道1時間半の往復3時間の時間は共働きや子育て世帯にとって、喉から手が出るほど貴重な時間。
ただただ通勤に終わらせてしまうのは勿体無いです。
そこで通勤時間に音声で自己啓発の勉強をすることで、生活を豊かにすることを提案します。
共働き子育て世帯に本を読んだり、セミナーに参加するような時間はありません。
だからこそ通勤時間の使い方で違いを生み出すしかありません。

ちなみに私は社会人3年目からずっとこの方法で知識を得るようにしてる!
具体的におすすめの勉強内容を3つ紹介しますので、最後まで読んでみてください。
共働き子育て中でも
「自分の時間」が欲しい方におすすめ!
| 項目 | 画像 | おすすめ | 悩み解決 | 時短効果 | 金額 | メリット | デメリット | おすすめ度 |
| 冷蔵宅配食 |  | つくりおき.jp | 夕食 | かなり大きい | 一食 798円〜833円 | 弁当や冷凍にも使える | 継続すると コストが大きい | |
| 弁当宅配食 |  | ライフミール | お弁当 | 大きい | 一食 404円〜530円 | 使うほど安い | 量が少ない | |
| ウォーター サーバー |  | ピュアライフ | ミルク 水筒 | 普通 | 月額3,300円 | 解約金無料 | 注水が手間 | |
| 幼児食宅配食 |  | mogumo | 子どものご飯 | 普通 | 1食 538円〜580円 | ストック しやすい | 定価は少し高い | |
| おもちゃの サブスク |  | ChaChaCha | 収納 片付け | 少し | 月額3,910円〜 ※プランによる | 知育効果 | リクエストは 3点まで | |
| 時短家電 |  | 食洗機 コードレス掃除機 衣類乾燥機 | 洗い物 掃除 洗濯 | 大きい | それぞれ 数万円レベル | 効果が持続的 | 最初にお金がかかる | |
| ふるさと納税 |  | 日用品 | 買い物 | かなり少し | 自己負担2000円 | 節約 | 収納の場所が必要 |
詳細はこちらの記事でまとめています。
片道1時間半を実際に続けて困ったこと
保育園の呼び出しに間に合わない
子どもが急に熱を出したとき、保育園からの電話が鳴ります。
しかし、職場から片道90分もかかると、すぐには動けません。
結果、妻や親に頼るしかないという辛さがあります。
さらに問題なのは、「少しだけ職場に行く」ができないこと。

勤務地が近いときは妻と交代で行くことができてた…。
長期に子どもが休まないといけない時、勤務地が遠いのは致命的な問題でした。
オイル交換を頻繁にするのが面倒
車通勤で往復3時間を毎日走ると、1か月の走行距離は4000kmを超えることも。

ちなみに往復160km!
その結果、オイル交換がすぐに必要になります。
ただでさえ時間がない休日に、月に1回のオイル交換は時間的にも金銭的にも負担でした。
朝の時間が短すぎて大変すぎる
朝6時40分に出る生活だったので、起床は5時台。
そこから朝食づくり、着替え、保育園準備と、分刻みのスケジュールが始まります。
子どもが機嫌よく支度できるとは限らず、「服イヤ!」「まだ眠い!」と泣かれることもしばしば。
もちろん、そんな生活がいつまでも元気に続けられず、体調を崩してしまうことも…。
「このままじゃやばい」と感じてから、まずはつくりおき宅配食サービスを導入しました。

毎朝お弁当を作ってた頃は地獄だったね。
おすすめのつくりおき宅配食サービスについてはこちらの記事でまとめているので、合わせて読んでみてください。
全国平均の通勤時間と比べてみると…
「自分の通勤は本当に長いのか?」と感じたときは、全国のデータと比べてみるのがおすすめです。
- 全国の片道通勤時間(中央値):
家計を主に支える雇用者の片道通勤時間は28.1分(総務省「住宅・土地統計調査 2018」)。
出典:e-Stat(政府統計の総合窓口) - 1日あたりの通勤・通学の平均時間:
10歳以上全体の「通勤・通学」平均は1日31分(総務省「社会生活基本調査 2021」)。
出典:総務省統計局「社会生活基本調査 2021」
年間にすると、どれくらい違う?
全国の標準的な通勤は片道28分(往復約56分)。
それに対して、片道90分(往復3時間)の通勤では次のような差が生まれます。
- 1日あたり: 全国標準より約2時間多く通勤に消える
- 1か月(20日勤務): 約41時間=丸2日分
- 1年(240日勤務): 約495時間=約62日分(2か月以上!)
つまり、片道90分の通勤は「家族や自分のために使えるはずの2か月分の時間」を奪ってしまうのです。
ひと目でわかる比較表
表にすると以下のとおり。
| 通勤スタイル | 片道 | 往復/日 | 月の通勤時間 (20日) | 年間通勤時間 (240日) | 全国標準比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全国標準(中央値ベース) | 約28分 | 約56分 | 約18.6時間 | 約224時間 | — |
| ふりパパの体験(片道90分) | 90分 | 180分 | 約60時間 | 約720時間 | 約3倍 |
※月・年の時間は概算。勤務日数や実際の行程により増減します。

共働き×子育て中にはかなりきつかった…。
共働き子育て世帯が通勤中こそ勉強するべき3選

資産形成の勉強
「将来の教育費が不安」
「今の貯金で足りるか分からない」
そう感じている方は多いはずです。
実は、こうしたお金の悩みの多くは“知識不足”が原因です。
NISAやiDeCo、ふるさと納税、住宅ローン控除など、知っていれば得できる制度は年々増えています。
とはいえ、家でゆっくり本を読む時間なんてない…というのが子育て中の現実。
そこで役立つのが通勤時間の“耳学習”です。
今は聞くだけで学べる音声コンテンツがたくさんあります。

私は初めに『両学長のリベラルアーツ大学』の情報を片っ端から入れてきたよ。
1日30分の耳学習でも、1か月続ければ15時間。
知識ゼロの状態からでも、家計の見直しができるようになります。
副業の勉強
資産形成と同じく、副業の勉強もおすすめです。
私自身もこのブログ運営についてのインプットのほとんどは通勤中の音声で勉強しました!

ちなみにウェブ職TVを毎日勉強するようにしていたね。
副業は、知識ゼロから始めても大丈夫。
まずは情報収集から始めて、できそうなことを見つけることが第一歩です。
時事ネタやスキルの勉強
最後に、時事ネタやスキルの勉強がおすすめです。
例えば、政治や経済、コミュニケーションスキルなどについて勉強するようにしていました。

ちなみにYouTube大学をよく見ていた頃もあったよ。
通勤コストを“見える化”してみよう
長時間通勤は、時間だけでなくお金の面でも大きな負担になります。
毎日のガソリン代や車の維持費を「ざっくり計算」してみると、意外な出費の多さに気づけます。
毎月どれくらいかかっている?
- ガソリン代:
月の走行距離 ÷ 燃費 × ガソリン単価 = 毎月のガソリン代
例)往復160km × 20日勤務 = 3,200km/月
燃費12km/L、ガソリン170円/Lなら…約45,000円! - オイル交換:
走行距離が多いと1〜2か月ごとに交換が必要に。
費用は1回あたり約5,000〜8,000円。 - タイヤ・車検:
年間数万km走ると、タイヤ交換サイクルも早くなる。
車検も「走行距離加算」で部品交換が増えやすい。
年間コストのイメージ
| 項目 | 月額の目安 | 年間の目安 |
|---|---|---|
| ガソリン代 | 約45,000円 | 約54万円 |
| オイル交換 | 約6,000円 | 約7万円 |
| タイヤ・車検加算 | 約5,000円 | 約6万円 |
| 合計 | 約56,000円 | 約67万円 |
もちろん通勤手当は出ますが、とても満額は支給されません!

時間もお金もかかってしまうのが通勤…。
通勤にかかるコストを少しでも下げるために
通勤時間が長いと、消耗するのは時間や体力だけではありません。
交通費・車の維持費・ガソリン代など、見えない“出費”も確実に家計を圧迫しています。
だからこそ、日々の移動にかかるコストを“少しでも”減らす工夫が大切です。
ここでは、今すぐできる節約アイデアを3つご紹介します。
楽天ポイントで給油
車通勤の方は、ガソリン代に楽天ポイントを使用するようにしましょう。
楽天経済圏を活用していれば、それなりにポイントが貯まっている時があるはずです。
贅沢に使うよりも、燃料代に充てることで、確実にコストを抑えられるようにしておくのをおすすめします。

まとめ買いで手にした期間限定ポイントなどはすぐに使っちゃおう。
マイレージサービスに登録しておく
高速を利用する方はETCマイレージサービスへ登録しておきましょう。
使用回数に応じてポイントが付くなど、やらない理由はありません。

私はずっと登録しておらず、めちゃくちゃ損してた…。
ちょっと面倒なことをしっかりやっているか、やっていないかで、大きな差が生まれるので注意してください。
インターネットでタイヤ交換・車検を予約
車の維持費を少しでも抑えたい方におすすめなのが、ネットでのタイヤ購入・交換予約。
年間何万kmと走る場合は、タイヤもすぐに消耗します。
その際、インターネットで購入、交換予約をすれば通常よりも安く抑えることができることがあります。

ちなみに私は楽天市場を使用してるよ。
まとめ:通勤時間を“無駄な時間”で終わらせない工夫を
通勤に片道90分もかかる生活では、家族と過ごす時間も、自分のための時間も削られていきます。
「この時間、本当に必要?」
「もっといい使い方があるのでは?」
そう感じたときこそ、行動を変えるチャンスかもしれません。
通勤時間はたしかに長いですが、学びに変えることもできます。
・資産形成の耳学習で、家計の見直しを
・副業の情報収集で、将来の収入の柱を
・ニュースやスキルのインプットで、教養を深める
また、長時間の通勤で足りない家事・育児の時間は、時短のサービスなどを取り入れてカバーするようにしましょう。
時短についてはこちらの記事でまとめているので参考にしてください。